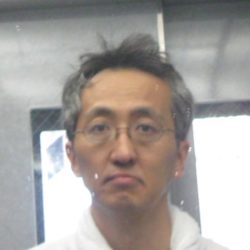密教には加持思想という思想が存在する。
加持思想とは、仏の不可思議な力が行者自身に加わり行者自身がその加持力により、ざまざまな神秘的な力が発揮出来るという思想のことをいう。
書籍『空海辞典 金岡秀友 編集 東京堂出版』の中で、加持、加持祈祷という意味について次のように解説されている。
加持=仏の不思議な力が我に加わり、我はその力を持つべく努めること。
実際には、さまざまな修法や儀式によって、仏の力を自分の上に得ること。
加持祈祷=加持とは、本来、仏の不思議な力によって加護されること。
仏の力の「下にたつ」ことをいう。
今は亡き政治評論家の竹村健一氏は自身の著書「竹村健一流 開き直りのすすめ 自分の弱さがバカらしくなる腹の据え方 竹村健一著 青春出版」の中の「うまくいったとき他人に感謝できないとダメになる」という章句の中で、竹村健一氏は密教の加持思想について書かれたとしか思えないような内容が書かれていたのでここで紹介したい。
「(竹村健一氏が)この間、霊の研究をしている人と話し合う機会があった。
なかなか面白いことを言っていたから、ここで紹介してみよう。
モーツァルトやベートーベンというような天才が死ぬ。
そいいう大天才でも、死ぬときに「もうオレはやりたいことを全部やり終えた」と思って死ぬ人は、大変に少ないという。
やっぱり、やり残した仕事がある。
それで、その霊が昇天して、今度は上の方から地上を見ていて「あっ、あいつに私のやり残した仕事をやらせてみよう」と思うというのである。
そうすると、たとえばベートーベンの霊が1人の男の後ろについてしまう。
もともとベートーベンの霊の目にかなった人物だから、ある程度の素質がある。
そこにベートーベンの霊がつくわけだから、たちまち素晴らしい演奏ができたり、コンクールで1位になったりする。
世間はベートーベンの生まれ変わりだ、という言葉でもてはやしたりする。
ところが、その霊の研究者が言うには、コンクールで優勝した男が、オレはやっぱり素晴らしい才能があるんだ。
天才なんだと思ったり、傲慢になると、とたんにその霊が去っていくという。
よく、昔は神童(しんとう)、いまはただの人、という言い方をするし、現実に、作家の世界でも芥川賞をとったのはいいが、その後、鳴かず飛ばずという人がいる。
コンクールで優勝しながらも、ダメになっていく演奏者もいる。
それは、せっかく後ろについてくれた天才の霊が、その人を見切って、どこかへ行ってしまうからだというのだ。
したがって、何かを目指して、それがたとえうまくいったとしても、それは自分だけの実力でできたと思わないで、ありがたい霊がオレの後ろについてくれているんだ。
ありがとう、ありがとうと、感謝しながらやっていくと、天才の霊はいつまでもついていてくれる。
それではじめて、長い期間にわたって素晴らしい仕事ができる、というわけだ。
これは本当か嘘かというのは誰にもわからないが、そう信じていたほうがいいと私は思う。
私(竹村健一氏)の話をテレビで聞いていたり、あるいは講演に来てくれた人も、私(竹村健一氏)がけっこう偉そうな態度でやっていると思うことがあるだろう。
しかしそれは、私(竹村健一氏)がこうしていられるのも、それは神様のお陰だといつも思っているからだ。
つまり、私(竹村健一氏)が勝手ながらもみんなの前で話ができるのは、神様がついていてくれるからだと思っている。
霊の研究者の話を聞いて、私(竹村健一氏)がこれまで神様と言ってきたが、それを霊と言い換えてもいいと思う。
いずれにしても、人間は自分ひとりでは生きていけない。
いろんな人の助けがあって、立派なことが初めてできる。
だからこれは霊に限らず、何かうまくいったときに、それを自分ひとりでできたと思わないで、友達だとか家族だとか、いろんな人の助けがあったからできたんだと、常に感謝の気持ちを忘れないことだ。
とにかく何をするのでも、いつも自分ひとりでできたんだと思わないで、感謝する気持ちを持ち続ければ、長い期間いい仕事ができると私(竹村健一氏)は思っている。
読者のみなさんも、ぜひそうして生きていったらいいと思う。」と書かれている。
さて、この竹村氏の話の中で傲慢や慢心についての話が出てきたが、仏教の教えには、慢心、おごり高ぶりの心を抑え、止滅すべきことが次のように説かれている。
「泥沼をわたりおわって、村の棘(とげ)を粉砕し、慢心を滅ぼすに至った人 ━ かれこそ修行僧と呼ばれるのである。」
(感興のことば 第三十二章 五十一 参照。書籍『ブッダの真理のことば 感興のことば 中村元訳 岩波文庫』290頁参照。)
また、お釈迦様は成道して間もない頃、次のような詠嘆の詩を説かれたと伝えられている。
「満足して、教えを聞き、真理を見るならば、孤独は楽しい。
人々に対して害心なく、生きとし生けるものに対して自制するのは、楽しい。
世間に対する貪欲を去り、もろもろの欲望を超越することは楽しい。
(おれがいるのだ)という慢心を制することは実に最上の楽しみである。」
(感興のことば 第三十章 十八 十九 参照。)
(書籍『ブッダの真理のことば 感興のことば 中村元訳 岩波文庫』270頁参照。)
(パーリ文献 律蔵経典 サンスクリット文献 阿含経 『四衆経』)
(書籍『輪廻する葦 桐山靖雄著 平河出版』92頁~93頁 参照)
書籍『空海辞典 金岡秀友 編集 東京堂出版』25頁~27頁 参照。
書籍『竹村健一流 開き直りのすすめ 自分の弱さがバカらしくなる腹の据え方 竹村健一著 青春出版』207頁~210頁 参照。
書籍『ブッダの真理のことば 感興のことば 中村元訳 岩波文庫』270頁 290頁参照。
 |
価格:7100円 |
![]()
 |
【中古】 竹村健一流開き直りのすすめ 自分の弱気がバカらしくなる腹の据え方 / 竹村 健一 / 青春出版社 [単行本]【宅配便出荷】 価格:278円 |
![]()
 |
ブッダの真理のことば・感興のことば (岩波文庫 青302-1) [ 中村 元 ] 価格:1210円 |
![]()
 |
価格:1980円 |
![]()