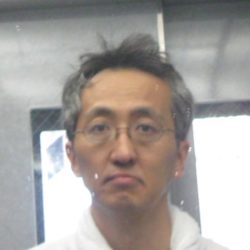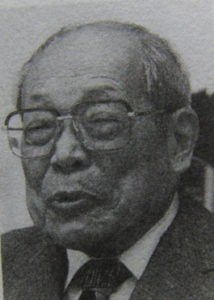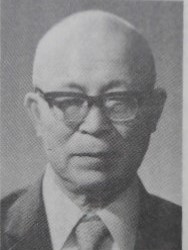日本や中国において、長い間、大乗仏教が信仰され、特に、日本において大乗経典と呼ばれる法華経や阿弥陀経などの大乗仏教が独占的に信仰され、その一方、阿含経というお経は小乗仏教、小乗経典として、軽視、もしくは、ほとんど無視されていた経典であった。
日本の仏教は千年以上の長きにわたり、阿含経を劣った小乗経典、つまり、自分だけの悟りを求め、自己のみが救われる事を目指す利己的で、レベルの低い卑しい経典とみなされていた。
また、出家しなければ救われない出家仏教の経典ともいわれてきた。
今から約1400年以上前の中国において、高僧、天台大師智顗(チギ)が立てた五時教判という教相判釈があるが、その教相判釈によると法華経、涅槃経が最も高い大乗の教えであり阿含経は最も低い小乗の教えであると結論づけされている。
その為,日本において、阿含経に対する研究や信仰はほとんどなされなかったが、近年文献学の目覚しい発展、パーリ語、サンスクリット語等の原語での仏典研究、著しい学術的進歩により阿含経典(パーリの五部 漢訳四阿含)こそが仏教の開祖であるお釈迦様が実際にお説きになった内容、もしくは、極めて近い内容の経典であると学問的に認められている。
この事についてインド哲学、仏教学の世界的権威(故)中村元 博士(1912~1999)は著書「バウッダ(佛教) 中村元 三枝充悳 共著 講談社学術文庫」において次のように解説されている。

中村 元 博士(1912年~1999年)
「現存のアーガマ(阿含経)を、そのまま「釈尊の教え」に直結することは、あまりにも短絡化しすぎており、今日の仏教学からすれば、むしろ誤りとみなされる。
ただし、釈尊の教えと仏弟子達の言行などは、そして、最初期ないしは初期の資料は、アーガマ(阿含経)にしか存在していないのであり、多数の大乗経典 (これを日本人は「釈尊の教え」そのものと誤解し「仏教」として受容してきた)には、求むべくもないことが明白である以上、何よりもアーガマ(阿含経)の解明に専念する仏教文献学が必要不可欠の前提とされる。
そして、それは、近代学問としてすでに100年以上の年月を刻んで、今日もなお営々として継続している。」とある。
また、仏教学者の(故)平川彰(ひらかわあきら)博士(1915~2002)は仏教経典の阿含経(あごんぎょう)について自身の著作である「インド仏教史 上巻 平川彰著 春秋社」という書籍において以下の主旨、概要の解説をされている。
「阿含経はアーガマ(Agama)、つまり伝わったもの、伝承されたものとも呼ばれ、仏陀釈尊の直接の教えが伝承されたものであることを示している。
しかし、これらの経典(阿含経)は仏陀釈尊の死後、仏陀釈尊の直弟子、仏陀釈尊の高弟達の記憶によって仏陀釈尊の教えの内容がまとめられ、又経典として書きとめられ伝来された為、伝承の間に仏陀釈尊の弟子の理解や解釈が付加され増広され、仏陀釈尊直説の教説が多少変化を蒙(こうむ)ったことは避けられなかったもしれない。
阿含経は仏陀釈尊の教えそのものではないかもしれない。
しかし、幾多の仏教諸経典の中で阿含経は仏陀釈尊の教えの内容を最も含んでいる経典であり仏陀釈尊の思想を求めるとすれば先ず阿含経の中に求められなければならない」
また、著名な日本の哲学者であった(故)梅原猛教授は自身の著作「地獄の思想 梅原 猛著 中央文庫」の中で
「釈迦の説法集が出来上がったのはむしろ釈迦の死後である。
釈迦の死後に様々な経典が作られた。
そして、その経典の中には釈迦の説というより弟子自身の説が混じるようになる。
後世の人々が釈迦の名において勝手に自己の学説を正当化する経典を作るようになる。
かくして、仏滅後五百年も六百年も過ぎて、なお釈迦の名において多数の経典群が作られていく。
そして、謎の人、釈迦の正体を解いたのは、ヨーロッパの近代文献学にもとづく仏教学であった。
文献学的な方法にもとづく仏教学は経典の成立年代を大体、考証的に明らかにした。
そして、釈迦の正説は、従来、日本においては、小乗と卑しめられてきた阿含部経典や律部経典にあることが分かったのである。
これは伝統的な仏教家にとっては大きなショックであるはずであった。
なぜなら、彼らが千数百年来、崇拝してきた仏教の経典が、釈迦の説ではなく、後世の説であり、彼らが卑しんできた経典こそ釈迦の説であることが明らかになったからである。
もし、このことを知ったら、親鸞や日蓮や道元はどのように驚いたであろうか。」
次に、パーリ仏典研究の世界的権威、(故)水野弘元博士(1901年~2006年)は仏教経典の源流について自身の著作「経典はいかに伝わったか 成立と流伝の歴史 水野弘元著 佼成出版社」において次のように説かれています。
「大乗仏教の般若の空思想や菩薩の波羅蜜の修道法もその源泉、源流は阿含経の中にあります。
インド大乗仏教の祖師と云われる龍樹菩薩や世親菩薩の著作において、阿含経の教説は大乗の教説と並べて権威的な典拠(典籍)として扱われ龍樹菩薩、世親菩薩の著作においてしばしば阿含経が引用されています。」
竜樹菩薩(チベット画)
竜樹菩薩(日本画)
また、ドイツの仏教学者、(故)ヘルマン・ベック(1875年~1937年)博士が著した「仏教(上)(下)岩波文庫 ベック著」という書籍においてヘルマン・ベック博士は仏教の実践の綱要を瞑想に見い出し、種々の経典、特にパーリ仏典の長部経典(漢訳では阿含経の長部経典にほぼ該当する)等を多く引用し瞑想、禅定に関する詳細な解説をしている。
さらにまた、(故)水野博士は自身の著作の「原始仏教」において阿含経を引用し
「那伽(ナーガ)は常(つね)に定(じょう)に在(あ)り。」と引用し実際に仏陀釈尊は禅定の熟達者であったと経典に伝えられている。
この経典の中で那伽(ナーガ)とは仏陀釈尊を意味する。
定とは瞑想、禅定を意味している。
南伝大蔵経の増支部経典においても
「那伽(ナーガ)は行(ゆ)くにも定(じょう)にあり、
那伽(ナーガ)は立(た)てるも定にあり、
那伽(ナーガ)は臥(ふ)すにも定にあり、
那伽(ナーガ)は座(ざ)せるにも定にあり」
とある。
また、漢訳仏典の中阿含経118の龍象経においても、
「龍行止倶定、坐定臥亦定、龍一切時定、是謂龍常法」
とある。
仏典中の龍(竜)とは優れた修行者を意味する事もある。
この経典の中の那伽(ナーガ)、龍(竜)とは仏陀釈尊を意味する。
仏陀釈尊は特に禅定(瞑想)に入っていない日常の精神状態であっても定(禅定)にあるのと同じように無念無想の精神統一を得られていたとされる。
水野弘元博士
参考文献
「バウッダ(佛教) 中村元 三枝充悳 共著 講談社学術文庫」
「インド仏教史 上巻 平川彰著 春秋社」
「インド仏教史 下巻 平川彰著 春秋社」
「地獄の思想 梅原猛著 中央文庫」
「経典はいかに伝わったか 成立と流伝の歴史 水野弘元著 佼成出版社」
「原始仏教 水野弘元著 サーラ叢書」
「仏教(上)(下)ベック著 岩波文庫」
「輪廻する葦 桐山靖雄著 平河出版」
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()
 |
|
中古価格 |
![]()